
2026.01.26
申請方法(DIPS)

2025.07.29

ドローンを特定の空域や方法で飛行させるには、航空法に基づく「飛行許可・承認」の取得が必要です。
申請は国土交通省のオンラインシステム「DIPS2.0」で行うのが基本となっており、申請者又は行政書士等の代理人が手続きを進められます。
しかし入力項目が多く、飛行内容や空域によって判断が難しい部分も少なくありません。
本記事では、飛行許可申請の全体像から、DIPS2.0の使い方、操縦者や機体に求められる条件、申請後の補正対応、そして許可取得後の義務までを詳しくまとめました。初めて申請を行う方や、業務でドローンを活用したい企業は、ぜひ参考にしてください。
目次
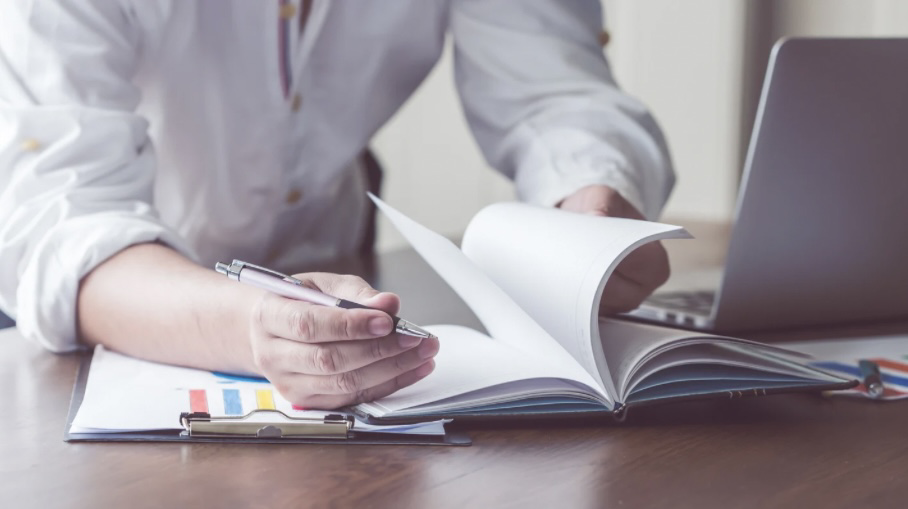
ドローンを特定の空域や方法で飛行させる場合には、航空法に基づく「飛行許可・承認申請」が必要となります。
ここでは、申請時に必要となる書類や提出情報について詳しく解説します。
ドローン飛行の許可申請には、DIPS2.0での正確な情報入力、資料の添付や具備が必要です。
申請の際には、主に以下の3点が求められます。
1.機体情報(基準適合確認書)
: 重量、最高速度 など
2.操縦者情報(飛行経歴・知識・能力)
: 飛行時間や知識など
3.飛行マニュアル
: 飛行の安全を確保するための運航ルールや体制を記載した文書
上記に加え、以下の追加情報や資料が使用する環境や状況によっては必要です。
これらの資料はDIPS2.0内で入力・添付又は別途具備する形式となっており、あらかじめ必要な情報を正確に把握しておくと申請をスムーズに進められるでしょう。
ドローンの飛行許可を申請する際は、まずドローンの機体登録が必要です。
飛行許可申請の前提条件となっており、登録が済んでいなければDIPS2.0での許可手続きは進められません。
機体登録は国土交通省によって定められており、屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローンに登録が義務付けられています。
仮に無登録で飛行した場合は「航空法違反」に該当し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意しましょう。
機体登録が完了すると、国から「登録記号」が発行されます。
発行された登録記号は、機体の見やすい位置に剥がれない方法で明示しなければなりません。
例として、25kg未満の機体であれば「文字の高さを3mm以上とする」といった明記基準が定められています。
また、リモートID機能の搭載も原則義務化されており、未搭載の機体には外付け機器での対応が必要です。
ドローンを運用する際は必須の項目となるため、これらの漏れがないように対応しましょう。
ドローンの飛行を考えているなら、飛行許可が必要な場所であるかも確認しましょう。
「飛行許可・承認の対象となる空域や飛行方法」に該当する場合、航空法で特定の空域や方法での飛行に対して、国土交通省の許可が義務づけられています。
主な区分は4つあり、それぞれ以下の通りです。
1.空港などの周辺の上空
:航空機の離着陸の安全を確保するため厳しく規制
2.地表または水面から150m以上の高さの空域
:空の安全確保の観点から制限
3.人口集中地区(DID)の上空
:落下リスクの高い場所として特に慎重な取り扱いが必要
4.緊急用務空域の上空
:消火活動など、緊急の用務を行うために指定された空域
このほか、空域に関係なく以下に該当する場合も国土交通省の承認が必要とされています。
これらの条件に該当するか否かを判断する際には、DIPS2.0、地理院地図のほか、「ドローンフライトナビ」を活用するとよいでしょう。
事前に申請の必要の有無を明確にしておけば、違反リスクの回避につながります。
飛行許可・承認を得るには、操縦者が一定の経験と知識、技術を有していることが大前提です。
ここでは、航空法および審査要領に基づく操縦者の要件について詳しく解説します。
ドローンの飛行許可を取得するには、原則として10時間以上の飛行経験が必要です。
これはドローンを「実際に飛ばした時間の合計」であり、操作回数ではないため注意しましょう。
また、申請する飛行内容に応じて、対応する飛行経験も変わります。
たとえば「夜間飛行」の申請を行う場合には、夜間の離着陸やホバリングの訓練を積んでおかなければなりません。
「目視外飛行」を希望する場合は、モニター越しでの操作訓練や、万一の事態に備えた手動操縦への切り替え操作などの経験が求められます。
飛行経歴は自己申告形式となりますが、虚偽の記載を行った場合には、許可取り消しなどの法的措置の対象です。
操縦者は、ドローンに関する航空法や関連するルール、そして安全飛行のための基本知識を身につけている必要があります。
基本知識に含まれるのは、以下のような内容です。
特に、夜間や目視外飛行などリスクが高まる運用においては、操縦者の知識レベルがそのまま飛行の安全性に直結します。
そのため、国土交通省のガイドライン等を熟読し、必要に応じてドローンスクールで外部講習を受けることが望ましいでしょう。
DIPS2.0では、知識の有無についても申請時に問われます。
所定の項目に対する入力が求められるため、事前の準備が必要です。
ドローンの操縦能力についても、一定の水準が求められます。
ここでいう「能力」とは、機体を安定的に操作し、計画どおりに離陸・飛行・着陸を実行できるスキルのことです。
加えて、突発的な状況においても、適切に対処できる判断力や反応速度も含まれます。
自動航行中の異常や通信遮断など、トラブル時に手動操作へ即座に切り替え、安全に着陸させる能力はきわめて重要です。
このようなスキルは実機による反復訓練によって磨かれるものであり、申請者が技術を備えているかも審査の対象となります。
なお、DIPS2.0ではこの操縦能力についても、飛行経験や訓練の内容、操作履歴などの入力を通じて評価される仕組みになっています。
申請の際は自分の能力を過信することなく、客観的かつ正確な自己申告を行いましょう。
ドローンの飛行許可・承認申請は、国土交通省が提供するオンラインシステム「DIPS2.0」を利用して行います。
ここからは、申請方法の種類や手続きの考え方について事前に把握しておくべき要点を詳しく見ていきましょう。
DIPS(Drone Information Platform System)2.0は、ドローンの機体登録や飛行許可・承認、飛行計画の通報、事故報告、登録講習機関、技能証明、機体認証の申請などを一括して行えるオンラインシステムです。
従来の郵送・紙ベースの申請に比べ、処理が効率化され、審査の進捗もオンラインで確認できます。
同システムでは、操縦者情報や機体情報の事前登録、飛行内容の選択、添付書類のアップロードなどが可能です。
ドローン運用を行う企業や個人にとって、DIPS2.0は欠かせないツールといえます。
包括申請とは、同一の申請者が同様の飛行を反復的に行う場合に利用できる申請方法です。
申請者の手続き負担を軽減する目的で設けられており、最長で1年間有効な許可・承認を得られます。
包括申請は農薬散布、空撮、点検、報道取材など、業務で繰り返し飛行する場合に適した方法です。業務を行う際に必須となる基本の申請です。
なお、包括申請により許可を得た場合でも、個別の飛行許可申請や、飛行前の「飛行計画の通報」は欠かせません。
仮に怠った場合は罰則となる可能性があるため注意しましょう。
個別申請は、特定の日時・場所・目的に限った単発の飛行を対象とする申請方法です。
空撮イベントや鉄道付近のインフラ点検など、包括申請で飛行できない場合に適しています。
個別申請では以下の情報を詳細に入力し、都度審査を受けなければなりません。
包括申請に比べて柔軟性はあるものの、その都度申請が必要なため、業務用途では手続き負担が大きくなりやすい側面があります。
包括申請と個別申請の大きな違いは、飛行の頻度と条件の定型性にあります。
繰り返し実施される定型的な飛行であれば包括申請が有効です。
一方で、リスクが高く都度条件が変わる不定期な飛行には個別申請が適しています。
包括申請は、比較的簡易な入力で申請できますが、資料の具備や安全管理体制を明確にした飛行マニュアルの遵守が欠かせません。
個別申請では案件ごとに情報を個別に入力し直す必要があり、資料の具備や飛行マニュアルの遵守も包括申請同様に必須です。
基本的な個別申請・包括申請のほかに、DIPS2.0では事業者の負担を軽減するための申請方法が用意されています。
企業や団体による効率的な運用を支援する方法として挙げられるのは、代行申請や一括申請です。
それぞれの申請方法や活用方法について、詳しく見ていきましょう。
代行申請とは、操縦者本人ではなく、行政書士などの第三者が代理で申請を行う方法です。
専門知識を持つ代理人が申請を行うことで、審査通過のスピードや効率が高まるという利点があります。
また、申請時には不要となったが作成しなければいけない具備資料も対応してくれます。
特に初めて申請を行う企業や、飛行経路が複雑なケースでは、代行を活用することで実務上のリスク回避につながるでしょう。
一括申請は、複数の操縦者・機体を対象として、同一の条件下で一度に複数の申請を提出する方式です。
たとえば、インフラ点検を行う企業が、複数の作業員とドローンを同じ現場で運用する際に活用されます。
申請内容の統一性が保たれていることが前提となります。
結果として管理コストの削減にも寄与する申請方法といえるでしょう。
飛行許可・承認申請の手続きは、DIPS2.0上で所定の情報を段階的に入力していく形式で進めます。
この章では、実際の申請画面で求められる各項目について、入力の流れと留意点をまとめました。
DIPS2.0を使って初めて機体登録や飛行許可・承認申請を行う際、まずはDIPS2.0のアカウントを登録しましょう。
法人で申請する場合は「企業・団体の方のアカウント開設」を選択し、担当者情報や組織名、連絡先を登録します。
アカウント登録後は、マイページから申請・登録・通報など一連の操作が行えるようになります。
機体登録での本人確認には、マイナンバーカード(個人)やgBizID(法人)を用いることでスムーズな確認が可能です。
飛行許可・承認申請を行う際は次に、使用予定のある無人航空機(ドローン)をシステム上に登録する必要があります。
登録に含まれる情報は、機体の製造者、型式、重量、最高速度、制御方法などです。
すでに機体登録済みであれば、登録記号(JUから始まる番号)が自動連携されます。
未登録機体の場合は、あらかじめ登録手続きを完了させておく必要があります。
操縦者についても、氏名、連絡先、飛行経験時間、訓練履歴などの情報を登録しましょう。
10時間以上の飛行経歴があるか、また申請する飛行方法に必要な訓練経験があるかを問われる項目があります。
企業で複数の操縦者がいる場合は、それぞれについて個別に登録し、該当申請との紐づけが必要です。
DIPS2.0では、入力された情報に基づいて、飛行計画が航空法上の「カテゴリーⅡ」または「カテゴリーⅢ」に該当するかを自動判定します。
カテゴリーによって審査基準や具備書類が異なるため、このステップで申請の複雑度とリスクレベルを把握しておくことが重要です。
申請対象となる飛行の目的を「測量」「空撮」などから選択しましょう。
このとき、飛行予定期間や頻度、飛行時間帯(昼間・夜間)などの基本情報も併せて入力します。
包括申請の場合は、1年間の範囲で反復する予定の飛行目的の選択が必要です。
飛行予定場所については、地図画面上で範囲を指定する形式になっています。
地番や地名入力に加え、ポリゴン機能を使って飛行エリアを可視化することで、システム上での審査官との情報共有が容易です。
また、空港周辺やDIDなど、制限空域に該当するかどうかもこの段階で明確にできるでしょう。
加えて、飛行高度、距離制限(人・物件との距離)、飛行方法(目視外、夜間等)を入力し、それに応じて必要な承認区分が自動で申請書に表示される仕組みです。
ここでは、申請に使用する機体・操縦者の組み合わせを一覧で指定します。
1つの申請に複数の機体や操縦者を紐づけられますが、事前に登録しておいた情報を正確に選択し、飛行内容に適合しているかを再確認することが重要です。
たとえば、夜間飛行であれば夜間訓練を行った操縦者を選定する必要がありますし、リモートID未搭載の機体はリモートID特定区域の届出が必要なケースもあります。
仮に機体や操縦者が適切でない場合、違反となる可能性があるため、注意しましょう。
最後に、任意保険の加入状況(対人・対物賠償など)とその証明書類(保険証券の写し)をアップロードします。
保険への加入は原則義務ではないものの、安全管理体制としての信用性向上につながるため、業務利用では実質的に必須です。
ただし、最大離陸重量25kg以上の機体や、レベル3.5飛行を行う場合は、飛行許可・承認申請時に保険加入が必須となっています。
また、飛行中の緊急対応に備えて、操縦者本人または責任者の連絡先を登録する項目も設けられています。
事故時の即時連絡体制が整っているかも審査対象となる点は、覚えておくとよいでしょう。

DIPS2.0で必要情報をすべて入力・確認したら、申請に進みましょう。
申請前には、飛行エリア・操縦者・機体・飛行方法・添付資料などが一覧表示されるので、記載ミスや漏れがないかを慎重に確認してください。また、申請には使用しない具備資料も合わせて確認しましょう。
申請書すると、国土交通省で審査が開始されます。
通常は数日~2週間程度で審査が完了しますが、繁忙期や内容が複雑な場合は補正指示(修正依頼)が出ることもあるようです。包括申請で航空局標準飛行マニュアルを使用する場合は、1日で審査が完了することもあります。
審査中は、DIPS2.0のマイページで状況を確認できます。
仮に申請後に誤りや変更が判明した場合は、取り下げや補正などの対応を取らなければなりません。
また、申請が完了した後も、許可・承認書の発行が済むまではドローンを飛行させないようにしましょう。
DIPS2.0で申請後、国土交通省の審査中に「補正指示」が届くことがあります。
これは、申請内容や添付資料に不備・不足があった場合の修正依頼です。
たとえば以下のような内容に該当する場合、補正指示へ対応しなければなりません。
補正を進める際は、DIPS2.0にログインし、該当申請のステータスを確認しましょう。
指示にしたがって内容を修正して再提出すると、審査が再開されます。
通知はDIPS2.0のマイページと登録メールアドレスに届くため、内容の確認が漏れないように注意してください。
特に初回申請では、ミスが起きやすいため確認の徹底が必要です。
補正を正確に行えば許可取得までの時短にもなりますので、丁寧な確認・対応を意識しましょう。
補正対応が完了し、すべての審査項目に問題がなければ、申請は正式に「許可・承認」されます。
この時点で、飛行許可承認書がDIPS2.0のマイページからPDFで発行され、申請手続きは完了です。
なお、許可承認書には飛行可能な空域・期間・機体・操縦者・飛行方法などが記載されており、その内容に沿って運用しなければなりません。
また、実際に飛行させる際は許可承認書を印刷して携行するか、スマホやタブレットで画面表示できる状態にしておくのが推奨されています。
包括申請で取得した場合は、特定飛行を行う前に都度「飛行計画の通報」が必要です。
許可承認書が発行されても、事前通報なしに自由に飛ばせるわけではない点に注意しましょう。

許可・承認を得た飛行(特定飛行)については、事前に「飛行計画の通報」を行うことが義務化されました。
対象となるのは、以下の空域での飛行です。
このほか、空域に関係なく以下に該当する場合も事前に「飛行計画の通報」が必要とされています。
通報はDIPS2.0上で行い、飛行日時、経路、高度、操縦者情報などを入力しましょう。
通報情報はほかのドローンユーザーにも共有されるため、原則として飛行開始前までの完了が必要です。
ドローンの飛行前後には、日常点検を実施し、記録に残すことが推奨されています。
バッテリー残量やプロペラの状態、GPSの受信状況、リモートID機能の作動確認など、安全に関わる項目を定期的にチェックすることが重要です。
この点検は飛行マニュアルに基づいて実施し、その記録を保管しておきましょう。万が一の際にも安全管理体制の証明として機能します。
点検記録は、Excel形式などで保管する方法が一般的です。
許可・承認を受けたドローンで特定飛行を実施した場合には、飛行ごとの記録を残すことが義務付けられています。これは安全管理や後日の証明として非常に有用です。
記録には以下の内容を含める必要があります。
これらの管理には、定型フォームを用いて記録すると整理しやすくなります。
なお、民間企業が開発したアプリでも飛行日誌機能が実装されており、アプリに入力することで記録を残すことも可能です。
万が一ドローンの飛行中に事故が発生した場合、直ちに中止しなければなりません。その後、関係機関への報告を行うことが義務付けられています。
具体的に対象となる事案は、主に以下の通りです。
事故が発生した場合、負傷者がいれば直ちに救護措置を講じたうえで、DIPS2.0の「事故・重大インシデントの報告」機能から必要情報を速やかに提出しましょう。
DIPS2.0では報告内容に応じて、自動的に運輸安全委員会または地方航空局のどちらかへ振り分けられる仕組みとなっています。
これらの対応は、法令遵守はもちろん、企業としての社会的責任を果たすうえでも非常に重要です。
万が一の事態に備え、平常時から対応手順を明確にしておくことが安全運用の鍵となります。

DIPS2.0を使えば誰でもドローンの飛行許可は申請可能ですが、内容は複雑かつ専門的で、不備や補正が発生しやすいのが現実です。
そのため、近年では行政書士に申請を依頼するケースが増えています。
行政書士へ依頼するメリットとして挙げられるのは、以下の3つです。
特に初めて申請する企業や複雑な内容が含まれる場合、行政書士への依頼は効果的な方法となるでしょう。
法令遵守と安全管理を徹底したいと考えているのであれば、ぜひバウンダリ行政書士法人へお問い合わせください。

ドローンの飛行許可申請は、すべてが該当するわけではありません。
航空法が定める特定の空域や飛行方法に該当しない場合には、許可・承認がなくても飛行できます。
ただし、土地の所有者や施設管理者の許可は別途必要となるため、この点には注意しましょう。
ドローンの飛行許可申請は、原則として「国土交通省(地方航空局、空港事務所)」に対して行います。
現在は、オンライン申請システム「DIPS2.0」を通じて手続きするのが一般的であり、郵送申請は例外的な扱いです。
機体の重量が100g未満の場合、現行法では「無人航空機」には該当しません。そのため、航空法に基づく飛行許可や機体登録は原則不要です。
ただし、緊急用務空域、自治体による独自の飛行規制、公園内のルール、プライバシー保護など、ほかの法律・条例は適用されます。
あくまでも申請不要なケースが多くなるだけであり、完全に自由に飛ばせるわけではない点に十分注意しましょう。
DIPS2.0の入力例や申請書ひな形は国土交通省の公式サイトで提供されています。
「DIPS2.0操作マニュアル」では新規申請、包括申請、飛行計画通報などの入力手順が解説されているため、必要に応じて確認しておきましょう。
DIPS2.0以外の方法ですと、例外的に「郵送申請」での飛行許可申請が認められています。ただし郵送申請は処理に時間がかかるため、推奨されません。
オンラインでは受け付けられない申請内容の際に郵送申請を活用し、それ以外の場合はDIPS2.0を使用することでスムーズな申請手続きにつながります。
許可・承認を得ずに飛行禁止空域でドローンを飛ばした場合、航空法違反となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、無登録の機体を屋外で飛行させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、飲酒操縦や点検不履行などの違反も、別途罰則対象となるため、十分な法令理解が不可欠です。
DIPS2.0は、画面にしたがって情報を順番に入力する形式のため、初めてでも操作は比較的わかりやすく設計されています。
また、過去の申請情報を再利用できる機能や、飛行計画通報・事故報告の一元管理ができる点も大きなメリットです。
ただし、入力項目は多く、飛行内容に応じた知識も必要となるため、慣れないうちは内容の誤りに注意しなければなりません。
また、添付が省略できるようになった資料もご自身で作成して具備しておく必要があります。
DIPS2.0では飛行日誌は作成できません。紙、Excelデータや民間企業が提供している飛行日誌アプリを使用しましょう。
業務利用の場合は、日誌の継続的な記録が法令遵守と信頼性向上の両面で有効です。
ドローンの飛行許可・承認申請は、DIPS2.0を使えば誰でも行える仕組みですが、実際には航空法に基づく多くのルールや条件を正確に理解・判断しながら進める必要があります。機体登録や操縦者要件の確認、飛行空域のチェック、マニュアルの作成など、準備すべき項目は多岐にわたります。
特に業務利用での申請や、複雑な飛行(夜間中の目視外飛行、レベル3.5飛行など)では、手続きの複雑化が避けられないため、行政書士などの専門家に依頼するのも有効な選択肢です。
許可取得後も、飛行計画の通報や日常点検、事故報告など、適切な情報管理と安全運用が求められます。法令を遵守しながら、安心・安全なドローン飛行を実現するために、本記事の内容を参考に確実な準備を進めましょう。
バウンダリ行政書士法人では、ドローンの飛行許可申請に関する無料相談を受け付けております。
本記事で紹介した内容はもちろん、それ以外の疑問点・不明点をお持ちの場合は、ぜひ一度お問い合わせください。

バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。