
2026.01.26
申請方法(DIPS)

2025.07.30
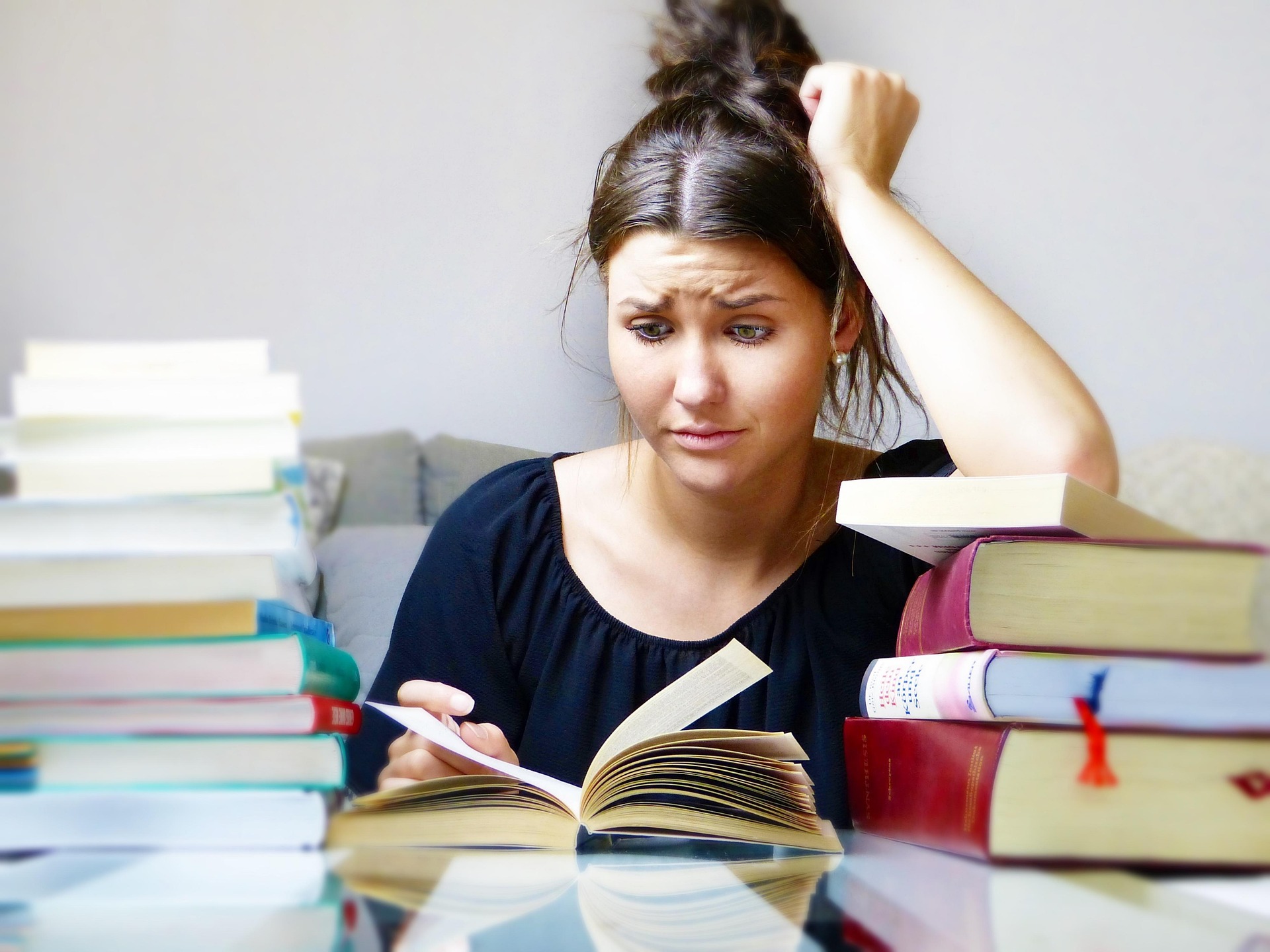
屋外で100g以上のドローンを飛ばす際には、機体登録が必須です。2022年6月から、小型ホビードローンも含めて登録が義務化されました。
未登録で飛行すると法令違反とみなされ罰則の対象になる可能性があります。
しかし「どのような手続きが必要なのか」「制度の目的は?」など、不明点を抱えている方も多いでしょう。
本記事では、ドローンの機体登録制度の概要から登録の流れ、リモートIDとの関係、さらには費用や注意点まで、制度の全体像を初心者にも分かりやすく解説します。
目次

ドローンの「機体登録制度」では、100g以上の無人航空機に対し、所有者情報の登録を求めています。
登録は有効期間3年で、原則期限の1ヶ月前から更新申請を行います。
期限内に更新しなかった場合は機体登録が抹消され、屋外の飛行はできません。
仮に飛行させた場合、航空法違反に該当し、罰則対象となるため注意が必要です。
ここからは制度が導入された背景や具体的な要件について詳しく解説します。
ドローンの機体登録が必要な理由は、所有者の特定と機体管理が欠かせないためです。
近年ドローンの活用が拡大する一方で、重要施設上空での飛行や墜落事故が多発しており、安全管理の強化が急務とされています。
機体登録をしておくことで事故や違反飛行が発生した際、登録情報を基に所有者を迅速に特定できます。
また、登録の義務化は利用者に安全意識を促し、無責任な飛行の抑止にも役立ちます。
登録情報を関係機関と共有しておくことで、テロ対策をはじめとした安全保障上のリスクに対応できる体制を整えられます。
ドローンの機体登録制度は2022年6月に義務化され、登録対象が100g以上の機体に拡大されました。
2022年6月20日に改正航空法が施行され、これまでは対象外とされていた200g未満のホビー用ドローンも含め、100g以上のすべての無人航空機が登録義務の対象となっています。
この改正により、制度開始前に設けられていた経過措置(2021年12月20日からの事前登録受付)は終了し、すべてのユーザーが法的義務を負うことになりました。
未登録状態でドローンを飛行させた場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意しましょう。
航空法における無人航空機とは、100g以上で遠隔操作や自動操縦が可能な機体を指します。
航空法第2条第22項では、無人航空機を以下のように定義しています。
航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの
なお、この100gの重量計算には、プロペラガードやカメラなど、後から取り外し可能な付属品の重量は含まれません。
100g未満の機体は「模型航空機」に分類されるため機体登録は不要ですが、飛行場所によっては航空法の規制対象となる場合があります。
ドローンの機体登録は原則として、国土交通省が提供する「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」を通じて行います。
申請は24時間受け付けており、紙媒体と比較すると割安な手数料での申請が可能です。
なお、DIPS2.0で機体登録を申請する際は、以下の情報が必要になります。
オンラインで申請する場合の手数料は最大1,450円ですが、申請方法によって費用は異なるため、確認しておきましょう。
DIPS2.0では、機体登録と飛行許可申請を一元管理できます。
一元管理によって登録済みの機体情報は、そのまま飛行申請時に呼び出せるため、手続きが簡素化されて入力ミスの防止にもつながるでしょう。
機体登録後に発行される登録記号を連携しておけば、その記号を選択するだけで申請書類に反映されます。
これにより、複雑だった飛行許可の申請が効率的に行えるようになりました。
法人や個人事業主は、事前に「gBizID」の取得が必要です。「gBizID」とは、法人・個人事業主向け共通認証システムを指します。
gBizIDを用いて機体登録をDIPS2.0で行うために、デジタル庁が提供する「gBizIDメンバー」または「gBizIDプライム」を取得しておきます。
また、「gBizIDプライム」を取得するためには、原則、印鑑証明書を添えた申請書を郵送する必要があります。
取得までに2週間程度かかることもあるため、ドローンの導入を検討している法人は、早めに準備しておくとよいでしょう。
リモートIDは、ドローンの機体情報を発信する機器のことです。
2022年6月20日以降、原則として、無人航空機に該当するすべての機体に搭載が必要となりました。
車でいうナンバープレートのようなもので、機体の追跡性や安全性を高める役割を果たします。
2022年6月20日以前に登録された機体は、リモートIDの搭載が免除されていました。
一定期間の経過措置とされていましたが、更新時には搭載が必須となるケースが増えてくるでしょう。
DIPS2.0を利用すれば、ドローンの機体登録をオンライン上で完結できます。
ここでは、アカウントの開設から申請完了、審査や手数料納付までの全体的な流れをステップごとに詳しく見ていきましょう。
DIPS2.0による登録は、アカウント開設・本人確認・情報入力・審査・手数料納付の5段階です。
ドローン機体登録は、DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)にアクセスし、以下の手順で進めます。
登録記号発行後、正式に登録が完了し、飛行許可申請などの手続きがスムーズになるでしょう。
DIPS2.0を利用するには、アカウントの開設が必要です。
アカウントの開設はDIPS2.0の公式サイトより行えます。
まずは公式サイトへアクセスし、トップページの「ログイン・アカウント作成」を押下した後、個人と法人・団体のどちらに該当するかを選択しましょう。
アカウントの分類を選択すると、画面上に利用規約が表示されます。
無人航空機の飛行ルールと合わせて確認し、チェックボックスを入力してください。
なお、利用規約や飛行ルールについては全文読まなければ、チェックできません。
利用規約に同意した後、アカウント開設の画面に遷移します。
開設画面では氏名や住所などの個人情報と合わせて、メールアドレスやパスワードの入力を進めましょう。
入力後「確認」を選択し、登録したアドレスに届いたメールを確認してください。
メール内のURLをクリックすると、アカウントの開設は完了となります。
DIPS2.0のアカウント開設が完了した後は、機体の新規登録に進みましょう。
本人確認は以下3通りの方法があります。
3つのうち、マイナンバーカードや運転免許証を使用する方法は、オンラインで完結するため手続きがスムーズです。
なお、代理申請の場合は、別途本人確認書類が必要です。
機体所有者の情報については、氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどの基本情報を入力します。
法人の場合は法人名や法人番号も必要です。
なお、既製品の機体か改造・自作した機体かによって登録内容が異なります。
自身の機体がどちらに当てはまるのか、事前に確認しておくことも大切です。
ドローンの登録者と使用者が異なる場合、実際に使用する人の情報登録も必要です。
たとえば自身が所有しているドローンを友人が常日頃管理して使用する場合、友人を使用者として登録します。
法人の場合は「法人番号が異なるかどうか」が判断基準です。
詳細については国土交通省が登録方法に関する資料を出しているため、参考にしながら使用者情報を入力しましょう。
必要事項の入力後、申請内容を確認し、問題がなければ送信します。
申請後は登録したメールアドレスへ「各種手続きお知らせ」が届くため、認証URLへアクセスしましょう。
問題なくアクセスができたら、機体登録は完了です。認証後は「申請受付完了」がメールで届きますが、万が一確認できない場合は申請が完了していない可能性があります。
このような場合は、窓口へ問い合わせするとよいでしょう。
登録申請後は、航空局による内容審査が行われます。
審査期間は、書類に不備がなければ通常1~5開庁日ほどかかります。
マイナンバーカードなどを用いたe-KYCを利用した場合は、より短期間で処理できる可能性が高いです。
また、手数料を納付してから登録記号が発行されるまでに、1~5開庁日を要することも覚えておきましょう。
全ての手続きが即日完了するケースもあります。
申請状況の確認は、DIPS2.0より行えます。
「申請状況一覧」から審査状況を確認し、「手続き完了」となっていれば問題ありません。
審査中の場合は「手続き内容確認中」と表示されるため、改めて状況を確認しましょう。
国土交通省から「手数料納付のお知らせ」がメールで届いたら、1ヶ月以内に納付します。
なお、本人確認方法によって納付方法は異なります。詳細は以下の通りです。
本人確認方法
納付方法
支払いが完了すると、登録記号(JU+英数字10桁)が発行され、登録済み機体としてDIPS2.0上に反映されます。

DIPS2.0での登録が完了すると、登録記号が付与され、ユーザーはその情報をシステム上で確認できるようになります。
また、この登録記号は機体へ表示する義務があるため、表示方法や注意点を正確に理解しておくことが重要です。
機体登録の完了後、国土交通省より付与された登録記号を確認しましょう。
登録記号は、DIPS2.0上の機体一覧や通知メールに表示されています。
登録が承認されると、アルファベット「JU」に続く10桁の英数字で構成された登録記号が発行されます。
登録記号は、DIPS2.0にログイン後「申請状況一覧」の「詳細」からいつでも確認可能です。
登録記号は、ドローンごとに一意に割り当てられる識別番号です。
航空法に基づき、登録された機体には1機ごとに登録記号が付与されます。
これは、無人航空機の「ナンバープレート」のようなもので、警察や関係機関が飛行中の機体を特定するための重要な情報です。
登録記号は機体の外から見やすい場所に、耐久性のある方法で表示します。
国土交通省のガイドラインによると、登録記号の表示に関する基準は、以下の通りです。
登録記号が不鮮明だったり、破損していたりする場合は、適切に修復するか、再表示する必要があります。
万が一、機体が第三者の敷地に墜落した場合などにも、登録記号を読み取れるかが重要になるため、適切に表示しておきましょう
登録内容に変更が生じた場合や登録の有効期限が近づいた場合は、DIPS2.0で変更または更新申請が必要です。
ドローン機体の登録は一度きりではなく、使用状況や機体構成に応じて情報を更新します。
変更や更新手続きの怠りは、登録の無効化や罰則につながる恐れがあるため、注意が必要です。
なお、変更が必要なケースは以下の通りです。
手続きはDIPS2.0にログインし、該当機体を選んで「変更届出」から入力して行います。
機体登録の有効期間は3年間で、継続使用する場合は更新申請を行う必要があります。
更新にも審査と手数料がかかり、オンライン申請の場合は890円です。
万が一更新を忘れた場合、登録記号が無効となり、飛行自体が違法になる恐れもあります。
DIPS2.0の通知機能や、管理カレンダーなどでスケジュールを管理するとよいでしょう。

ドローンを機体登録する際には、さまざまな疑問や不明点が出てくるかもしれません。
ここで紹介する質問内容を理解し、スムーズに手続きを進めましょう。
機体登録の代理申請には原則委任状が必要で、DIPS2.0の専用アカウントでのログインが必要です。
ドローンの機体登録は、所有者本人だけでなく、行政書士などによる代理申請も認められています。
代理申請を行う場合は、DIPS2.0で「代理申請者アカウント」を作成し、所有者の委任状を添付しましょう。
登録完了後の通知や管理は所有者側で行う必要があるため、委任内容を明確にしておくことが大切です。
代理申請のアカウントが不要なケースもあります。
自作機や改造機も登録可能で、シリアルナンバーは任意の英数字で設定できます。
市販されていない自作ドローンも、DIPS2.0を通じて登録可能です。
この場合、「製造者名」は「自作」または製作者の氏名を、「型式名」には任意の名称を入力します。
シリアルナンバーについては、重複しないよう自身で任意に設定しましょう。
たとえば「DIY202507A01」などのように、英数字の組み合わせで登録します
(出典:国土交通省|FAQ)。
ドローン機体の登録にかかる費用は、申請方法や本人確認の手段により、900~2,400円の範囲で変動します。
詳細はは以下の通りです。
複数機体を同時に申請する場合、2機目以降の登録費用が割引される制度もあります。
オンライン申請は、時間とコストを抑えられる点がメリットです。
DIPS2.0にログインして「所有機体一覧」から、自身の機体が登録されているかどうか、確認可能です。
「所有機体一覧」メニューでは登録済み機体が一覧で表示されます。
このとき、登録記号や申請日、有効期限などの情報も確認できます。
なお、第三者が他人の登録状況を調べることはできず、公開データベースなどは用意されていません。
正確な管理のためにも、登録記号と申請情報は自身で適切に保管しましょう。
以下に該当する場合、機体登録ができない可能性があります。
機体登録をする際は、上記に該当しないかを必ず確認しましょう。

バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。