
2026.01.26
申請方法(DIPS)

2025.08.19

ドローンを業務で活用する際、必ず直面するのが「飛行許可申請」という壁です。
特に空撮・点検・測量などを日常的に行う事業者にとっては、申請作業の手間が大きな負担となります。
そこで注目すべきなのが「包括申請」という制度です。
この記事では、包括申請の概要や種類、具体的なメリット、申請手続きの流れまでを、国土交通省の公式情報に基づいてわかりやすく解説します。
ぜひ参考にして、ドローンの包括申請に関する悩みや疑問の解消にお役立てください。
目次

ドローンの包括申請とは、ドローンを繰り返し飛行させる業務で同種の飛行を一定期間まとめて申請・許可できる制度です。
個別に何度も申請する手間が省け、継続的にドローンを使う事業者にとっては効率的な仕組みといえます。
農薬散布やインフラ点検、建設現場の測量、災害時対応、報道取材など、さまざまな業務に対応しており、明確な目的と安全対策があれば全国的な飛行許可を得ることも可能です。
これにより、現場対応のスピードと柔軟性が大きく向上します。
ドローンの飛行申請には「個別申請」と「包括申請」の2種類があります。それぞれの違いは、飛行範囲の柔軟性と申請頻度です。
個別申請は、飛行させる期間(内容によっては日時まで)、場所を毎回指定して申請します。
イベント撮影などの一時的な単発業務に適していますが、その都度の手続きが必要で非効率的です。
対して、包括申請は繰り返し行う飛行をまとめて申請できます。
農業・建設・報道などの定期業務に適しており、最長1年間自由に飛行可能です。
このように、業務が反復的・継続的である場合は包括申請が適しています。
効率的な運用のためにも、目的に応じた申請方式の選択が重要です。
包括申請は反復的な飛行を一括で申請できる制度ですが、飛行の性質に応じて2種類に分類されます。
それぞれの特徴と向いている業務について、詳しく見ていきましょう。
全国包括申請は、飛行場所を事前に特定せず、一定期間内に全国各地で繰り返し飛行する業務に適した方式です。
この申請は、現場ごとに飛行場所が変わるような業務において、手続きの効率化と柔軟性を大きく高めてくれます。
ただし、空港等周辺や地表から150m以上上空などの規制空域では追加で飛行許可申請が必要であり、現地の安全確認や土地管理者の許可取得も飛行前に求められる点に注意しましょう。
飛行経路包括申請は、特定の飛行ルートを反復的に利用するケースに適した申請方式です。
出発地から目的地までの飛行経路をあらかじめ地図上で指定し、そのルートに限って飛行が許可されます。
典型的な用途として挙げられるのは、配送サービスや、河川・送電線などのインフラ巡回、定期的なパトロール業務などです。
特定のルートを繰り返し飛行することで、安全性の確保や運航計画の安定化が図れるため、ルートの固定がメリットとなる業務に向いています。
この申請方式では、申請時にルートの詳細(出発点、到着点、飛行経路、経路幅など)を明確に指定しなければなりません。
得られる期間は最長1年で、全国包括申請と同様です。
現時点では利用シーンがやや限定されているものの、今後のドローン物流やレベル4飛行(有人地帯での補助者なし目視外飛行)の普及に伴い、活用の拡大が期待されている制度です。

ドローンの包括申請は、単なる手続きの簡略化にとどまらず、業務の効率化、コスト削減、柔軟な対応力の向上といった、多くの実務的メリットをもたらします。
ここでは、特に重要な3つの利点に絞って見ていきましょう。
包括申請の最大の魅力は、飛行のたびに申請手続きを行う必要がなくなることです。
個別申請では、飛行ごとに日時や経路を定めた申請書類を作成し、オンラインシステム(DIPS2.0)などを通じて提出しなければなりません。
そのため時間も労力もかかり、許可が下りるまでには平均して10開庁日程度の審査期間を要します。
一方で包括申請を利用すれば、一度の申請で最長1年間の飛行が許可されるため、突発的な業務や急な依頼にも即座に対応可能です。
たとえば、天候が急に好転した場合には当日すぐにドローンを飛ばすことができるでしょう。
ただし、不要なのは「許可申請」の部分だけであり、飛行前の安全確認、飛行計画通報や飛行日誌の記録義務は引き続き必要です。
この点を理解したうえで活用すれば、日々の業務負担を大きく軽減できます。
包括申請は、時間的にも金銭的(申請代行を依頼する場合)にも申請コストを削減できる制度です。
まず、時間的コストについては、個別申請で毎回必要な書類作成やDIPS2.0への入力作業を「年1回」に集約できます。
そのため、申請頻度が高い事業者にとっては、社内リソースの大幅な節約につながるでしょう。
また、金銭的コストについても、申請代行を行政書士に依頼する場合にその差が顕著です。
個別申請では1件あたり3〜7万円の費用が目安となります。一方で包括申請の相場は1件3〜5万円程度です。
そのため、年間で複数回の個別申請を行うより、包括申請を1回行う方が圧倒的に安く済むケースが多く見られます。
ドローンの業務は天候や現場状況に大きく左右されるため、柔軟なスケジュール調整が重要です。
その点で、包括申請は非常に優れた対応力を持っています。
個別申請では飛行日時を特定して許可を得ることもあるため、予定していた飛行が悪天候で中止になると新たな再申請が必要です。
変更申請で対応できる場合もありますが、それでも手間と時間は避けられません。
対して包括申請では、日程の変更や場所の柔軟な調整が可能です。
例えば「A地点での飛行が悪天候で中止になったが、同日にB地点での飛行に切り替える」といった対応も問題なく行えます。
このように、包括申請を取得しておけば、顧客の急なスケジュール変更や突発的な現地対応にも迅速に応じられるため、結果的に機会損失を減らし、事業の信頼性も向上します。

ドローンの包括申請は非常に便利な制度ですが、正しく申請を行うためには所定のステップを理解しておくことが重要です。
ここでは実際の申請の流れについて、3つのフェーズに分けて見ていきましょう。
申請作業を始める前に、まず自分の飛行計画が包括申請の対象となるかの確認が必要です。
包括申請は、以下のような条件で利用できます。
測量や農薬散布などのように毎回同じ業務で、ある程度の繰り返しが見込まれるなら、包括申請の対象です。
一方、イベント上空や空港等周辺など特別な審査が必要なケースでは包括申請が認められません。
まずは自身の業務内容がこれらの条件を満たしているかを確認し、それに応じた申請の準備を始めましょう。
包括申請には、大きく分けて3つの手段があります。
ここではそれぞれの申請方法について、詳しく見ていきましょう。
窓口申請は、地方航空局に直接出向いて申請書を提出する方法です。
担当者と直接相談しながら進められるメリットがありますが、地域や混雑状況によっては対応に時間のかかることがあります。
また、事前相談が必要な場合などには適している反面、遠方からの手続きには不向きなので今はほとんど利用されていません。
郵送(メール)申請は、必要書類を揃えて所定の宛先に送付する方法です。
窓口に出向く必要はありませんが、郵送日数や書類の不備による差し戻しのリスクがあります。
このことから、急ぎの申請や確実性を求める場合にはあまり適さないでしょう。
また、手元に控えが残らない点もデメリットとして考慮する必要があります。
こちらも窓口申請ほどではありませんが、あまり利用されていません。
現在、ドローンの包括申請で推奨されているのが、国土交通省が提供するオンライン申請システム「DIPS 2.0」を利用した方法です。
DIPS 2.0では、以下のような機能が提供されています。
DIPS 2.0では申請の進捗状況も確認できるため、わかりやすさと効率の良さに優れた手段といえるでしょう。
初回利用時にはアカウント登録が必要ですが、それ以降は簡単な入力作業でスムーズに申請できます。
なお、DIPS2.0を使った申請でも内容に不備があると差し戻しとなるため、申請内容の確認や事前準備が不可欠です。
また、2025年3月から一部の添付書類が不要となり簡略化されましたが、不要となった添付書類はしっかりと作成し、具備しなければいけません。
包括申請によって飛行許可を得た後も、ドローンの運用には飛行計画の通用や飛行記録の作成義務があります。
これは、安全管理や事後検証の観点から、国が操縦者に求めている基本的なルールです。
飛行日誌には、以下のような情報を記録する必要があります。
これらの情報は、紙やExcel、またはDIPS2.0上で管理することが可能です。
事故発生時に提出が求められる場合があるため、正確かつ継続的な記録が求められます。
罰則もあるので、抜け漏れが無いように行いましょう。
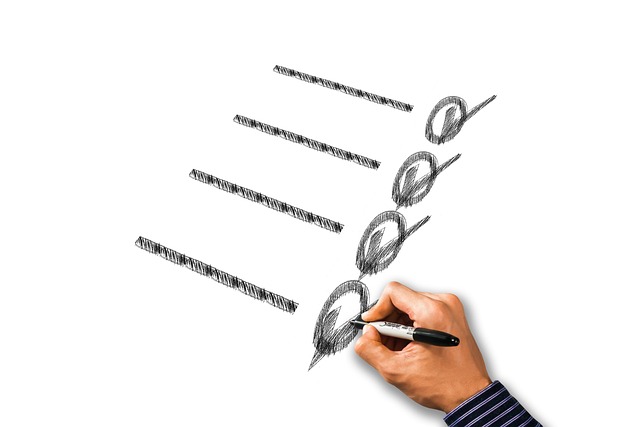
包括申請をスムーズに進めるには、必要な情報を事前に整理しておくことが欠かせません。
特に重要なのは、操縦者の情報、使用機体、保険、安全対策の4点です。
まず、操縦者については氏名や連絡先に加えて、10時間以上の飛行経験を証明する記録が必要とされますので、しっかり準備しましょう。
機体に関しては、型式や製造番号、仕様書(安全機能の記載があるもの)などを用意します。
機体が複数ある場合でも、すべてにおいて正確な登録が必要です。
また、対人・対物を補償する損害賠償保険の加入状況も求められます。
事故発生時の補償だけでなく、一部の飛行では加入していなければ許可が出ないものもあります。
安全確保体制を示す飛行マニュアルの提出も、忘れずに行いましょう。
通常時の飛行手順や緊急時の対応、禁止空域の確認方法など、国のガイドラインに沿った内容を整える必要があります。
これらの準備が整っていれば申請手続きが格段にスムーズになり、審査期間の短縮につながるでしょう。
航空局で準備している標準飛行マニュアルを使用する場合は、添付は不要です。
包括申請は非常に便利な制度ですが、すべての飛行に対して適用されるわけではありません。
飛行の場所や方法によっては、安全性の観点から包括申請の対象外とされており、個別に申請・審査を受ける必要があります。
ここでは、包括申請が認められない主なケースを3つに分けてまとめました。
まず、飛行場所そのものが包括申請の対象外となるケースがあります。
航空法では、第三者や航空機の安全を守るために「飛行禁止空域」が定められており、これらの空域で飛行する場合は、包括申請ではなく個別申請が必須です。
対象外区域の代表例は、以下を参考にしてください。
上記に該当する場合は個別にリスク評価や調整が求められるため、包括的な許可を出すことができません。
なお、誤解されやすいのが「人口集中地区(DID)」の上空です。
夜間飛行を除いて包括申請の対象に含めることが可能であり、適切な申請内容と安全対策があれば許可されます。
飛行方法そのものが包括申請の対象外となるケースがあります。
特に第三者へのリスクが高い特殊な飛行方法については、個別に審査が必要です。
対象外となる主な飛行方法には以下が含まれます。
これらの飛行は、個別申請で内容に応じた具体的な安全対策(立入禁止エリアの設置、補助者の配置など)を示すことで許可が得られることもありますが、包括的な許可を出すことは制度上想定されていません。
最後に注意すべきなのが、航空法上の許可と、土地管理者の許可は別であるという点です。
たとえ包括申請で国から飛行許可を得ていたとしても、飛行予定地が私有地や公園などの管理区域内である場合、トラブル予防のため、別途その管理者の承諾が必要です。
具体的に該当する場所は、以下の通りです。
この点を見落とすと、合法的な許可を得ていても迷惑行為とみなされかねません。
トラブルを避けるには、ドローンを飛行させるたびに土地の所有者や管理者のルールを確認しましょう。
ドローンを飛行させるすべての場面で包括申請が必要というわけではありません。
本来必要のない手間や時間をかけないためにも、申請が不要となる代表的な5つのケースについて確認しておきましょう。
航空法では、飛行許可が必要な飛行を「特定飛行」として定義しています。
以下の飛行内容であれば、原則として申請は必要ありません。
つまり、安全な環境でシンプルな飛行方法をとっている限りは、包括申請をしなくても合法的に飛行可能です。
ドローンの機体重量が100g未満(バッテリー含む)である場合、航空法の規制が少なくなります。
このため、一部の空港、一定の飛行高度、緊急用務空域でなければ航空法に基づく申請は不要です。
ただし、小型無人機等飛行禁止法の規制、地方自治体の条例や施設ごとの規則、またはプライバシーや安全に関する民法上の注意義務は引き続き適用されます。
申請は不要でも、無制限に飛ばしてよいというわけではない点に注意しましょう。
航空法は、屋外空域での飛行にのみ適用されます。
そのため、四方と天井が覆われている屋内(体育館、倉庫、スタジオ等)での飛行は規制対象外となり、包括申請を含む一切の申請は不要です。
ただし、施設の管理者による使用許可や、安全確保のための措置は別途施さなければなりません。
商業施設や学校などで飛行させる場合は、事前に確認・許可を得ることが望ましいでしょう。
ドローンを30m以内のロープやワイヤーで地上に繋いだ「係留飛行」も、一定条件下では申請が不要です。
これは、不意の逸脱や制御不能を防ぐための措置として有効であり、条件を満たせば一部の飛行許可申請は不要です。
不要となる飛行許可申請は、以下の通りです。
係留が有効となる条件の例は、以下の通りです。
ただし、特定飛行であることには変わりはありませんので、係留をしていても特定飛行を行う場合は、飛行計画通報や飛行日誌の作成は必要です。
2022年12月の国家資格制度導入により、特定の資格と機体認証の組み合わせを取得している場合、一部の飛行については許可申請が不要です。
例えば「二等無人航空機操縦士(必要な限定変更を取得している場合に限る)」の資格を持ち「第二種機体認証」を取得したドローンを使用する場合、例外的に申請不要となることがあります。
許可申請が不要な飛行は以下の通りです。
ただし、イベント上空、空港等周辺や150m以上の上空など、許可が必要な飛行もあります。
また、飛行計画の通報や飛行日誌の作成など、その他の義務も免除されるわけではありません。
現状では、こうした資格や機体の普及率はまだ高くないため、多くの操縦者にとっては引き続き包括申請が必要という前提で考えるのが妥当です。

ドローンの包括申請は非常に便利な制度ですが仕組みは複雑で、申請者から寄せられる疑問も多く見られます。
ここでは代表的な4つの質問について、詳しく見ていきましょう。
包括申請の有効期間は、最長で1年です。
ただし、国土交通省が申請内容、操縦者の経験、安全対策などを審査し、許可される期間は短縮される場合もあります。
安全性の観点から、3ヶ月や6ヶ月に制限されるケースもあることを覚えておきましょう。
「包括申請」と「飛行許可申請」は混同されがちですが、正確には包括申請は飛行許可申請の1つの形態です。
つまり、包括申請は「飛行許可申請」の一種であり、反復的な飛行の効率化を目的としています。
飛行内容が定型的であれば、包括申請の方が適しているでしょう。
ドローンの包括申請は法人・個人を問わずに可能です。
実際、フリーランスの空撮業者や個人事業主が申請するケースも多く見られます。
ただし、申請者が個人であっても、申請の要件(飛行経歴、機体情報、安全対策など)は法人と変わりません。
そのため、事前準備はしっかり行う必要があります。
業務として継続的にドローンを運用するのであれば、個人でも包括申請を行うメリットは十分にあると言えるでしょう。
ドローンの包括申請には、操縦者の飛行経験が重要な審査項目として含まれます。
基準として、10時間以上の飛行実績が求められています。
ただし、仮に基準を満たしていない場合でも、申請自体が不可能というわけではありません。
例えば、練習飛行を重ねて記録を蓄積したり、ドローンスクールでの訓練記録を提出したりするなど、代替的に技量を証明できる手段を用意することで、審査に対応できる可能性があります。
ただし経験不足が明らかな場合には、申請自体の却下につながることもあるため、飛行経験を積むことが望ましいでしょう。

ドローンの包括申請と個別申請は、飛行経歴の証明や安全マニュアルの整備、DIPS2.0での入力など、手続きが煩雑になりやすく、初めての申請では不安を感じる方も少なくありません。
そうした場合に有効なのが、行政書士などの専門家に申請を代行してもらうという選択肢です。
バウンダリ行政書士法人では、ドローンの包括申請に関するサポートを行っています。
確実な手続きはもちろんのこと、効率よく申請を済ませたいというニーズにも対応可能です。
特に、審査期間の短縮や申請の問題ない通過を望む場合には、専門家への相談が有効でしょう。
ドローンの包括申請に関する悩みや疑問を抱えているのであれば、ぜひ一度お問い合わせください。
ドローンの包括申請は、業務におけるドローン活用をより効率的かつ柔軟に行うための強力な制度です。
飛行のたびに申請を繰り返す必要がなくなるだけでなく、コスト削減やスケジュール変更への対応力の向上など、事業運営の実務面でも多くのメリットがあります。
一方で、包括申請はすべての飛行や操縦者に自動的に認められるものではありません。
適用範囲、必要な準備、対象外となるケースについて正確に理解しておくことが重要です。
制度の概要や申請の種類(全国包括・飛行経路包括)、注意点、申請不要なケース、代行利用の選択肢に至るまで、網羅的な知識を持つことで無駄なトラブルや申請ミスを未然に防げます。
この記事で紹介した内容をもとに、正しい手順でドローンの包括申請を進めてください。

バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。