
2026.01.26
申請方法(DIPS)

2025.10.21
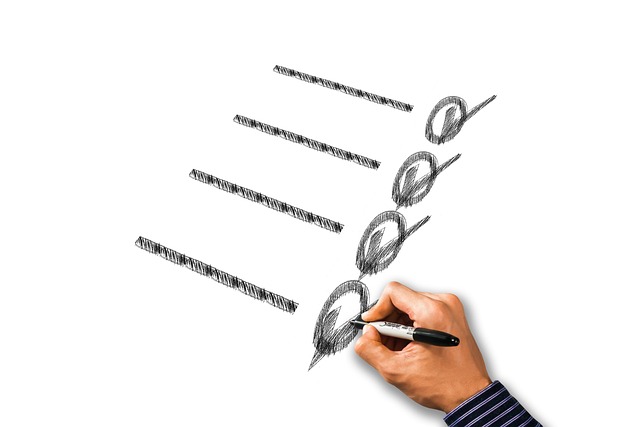
国家資格「無人航空機操縦者技能証明」の制度ができ、ドローン操縦士の育成は新たなビジネスチャンスを迎えています。
その中心を担うのが、国土交通大臣の登録を受けた「登録講習機関」です。
しかし、登録を受けるには、施設や設備、講師、修了審査員、使用機体など多岐にわたる厳しい要件を満たし、膨大な申請書類を整える必要があります。
初めて挑戦する方にとっては、制度の理解や実務面で大きなハードルとなるでしょう。
本記事では、登録講習機関として認定を受けるための要件や申請手続き、必要書類などを項目別にわかりやすく解説します。
申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
ドローンの登録講習機関の要件とは
施設要件
2-1. 施設の占有と利用形態の要件
2-2. 周辺環境と講義実施に適した要件
2-3. オンライン講習の共通要件
2-4. オンライン会議ツール(Zoom等)利用時の要件
2-5. 動画視聴型講習の要件
設備要件
3-1. 基本設備の要件
3-2. 実地講習の教材要件
空域要件
機体要件
講師要件
6-1. 共通の講師要件
6-2. 一等講習機関の講師の要件
6-3. 二等講習機関の講師の要件
ドローンの登録講習機関として登録を受けるまでの流れ
ドローンの登録講習機関として登録を受けるための必要書類
ドローンの登録講習機関としての登録に関するよくある質問と回答
9-1. 複数のスクールをまとめて登録することは可能ですか?
9-2. 登録にあたって手数料は必要ですか?
9-3.ホテルや旅館レジャー施設も利用してドローン講習(審査を含む)を行えますか?
9-4.講師要件の飛行経験にシミュレーターでの飛行経験は含まれますか?
ドローンの登録講習機関の登録手続きは申請代行で確実に
ドローンの登録講習機関の要件を確認して申請手続きを行おう
ドローン(無人航空機)の登録講習機関として国土交通大臣の登録を受けるためには、一定の要件クリアが必要です。
具体的には、適切な施設、講習に必要な設備、経験と知識を備えた講師陣、さらには基準を満たした使用機体の確保などが該当します。
そのため、ドローンスクールが登録講習機関として登録を目指す場合は、こうした条件を整備することが最初の関門となります。
そもそも登録講習機関とは、国の基準を満たしてドローンの国家資格を取得するための教育を提供する民間企業(法人)です。
登録講習機関のカリキュラムを修了した受講者は、国の実地試験が免除されるという大きな利点があります。
登録講習機関が誕生した背景には、ドローンの需要が建設・測量・点検・映像制作など幅広い分野で広がり、操縦ライセンスを持つ人材が求められるようになったことが挙げられます。
今後も国家資格取得の増加が見込まれることから、すでに各地に存在する民間のドローンスクールのノウハウとリソースを有効活用し、効率的に多数の操縦士を育成する仕組みを国が導入しました。
ここでは、ドローンの登録講習機関として国土交通大臣の登録を受けるための要件の一つである、施設要件を解説します。
施設要件は「建物や設備」のみを指すのではなく、講習(オンラインを含みます)を実施する際の環境も含みます。
配信拠点の環境が整備されていないと、通信が乱れたり講義の質が確保できなくなったりするためです。
受講者が安心して学べる環境を整えることが、施設要件に求められる本質といえます。
ドローンの登録講習機関として認定されるには、講習を行う施設をドローンスクールが占有していることが必要です。
占有施設であるか否かは、施設及び設備の概要書や不動産登記簿謄本、土地建物賃貸借契約書などの書類を通じて確認されます。
ただし賃貸物件やスポットで利用する施設であっても問題はなく、安定的に使用できれば条件を満たすことが可能です。
また、地域住民に開放されている公共施設や、特定の団体に所属する会員のみが利用できる施設を用いる場合も、活用が認められています。
講習を適切に実施するには、建物の周辺環境が学習の妨げにならないことが重要です。
交通騒音や利用制限などで授業に支障が出るような立地の場合は学習の妨げになります。
オンライン形式であっても例外ではなく、配信拠点となる施設が同じ基準を満たしていることが必要です。
オンライン講習は、リアルタイムでオンライン会議ツールを使用、イーラーニング形式(動画視聴型)のものがあります。
オンライン講習は、対面講習と比較して講師が受講者の理解度を確認しにくい環境にあります。
そのため、修了時には効果測定を行って学習成果を客観的に確認する仕組みが求められます。
なお、対面講習の場合は受講者の様子を講師が直接確認できるので、修了判定を比較的柔軟に行えることが特徴です。
したがってテストは必須ではなく、あくまで「推奨」にとどまっています。
そのほか、オンライン講習では受講者から寄せられる質問に迅速に対応できる態勢の整備も欠かせません。
オススメのイーラーニング形式の講習もあるので、活用を検討している企業はこちらからお問い合わせください。
こちらのリンクからお問い合わせいただくと、無期限割引の適用もございます。
Zoomなどのオンライン会議ツールを活用して講習を行う場合にも、明確な要件が定められています。
具体的には、講師と受講者がお互いを音声と映像で確認できる環境でなければなりません。
さらに、担当する講師は必ず講師要件を満たしていることが必要です。
また、一度に参加できる受講者は100名以内に制限されています。
動画視聴型講義を行う場合、動画の制作や監修の担当は講師要件を満たした自社所属の講師でなければなりません。
さらに、単に映像を流すだけでは不十分で、再生履歴や操作記録を通じて受講状況を把握できる仕組みが必要です。
登録講習機関として認定されるには、受講者の学習実績を確実に確認して公平で信頼性の高い教育を提供できると判断されなければなりません。
講習を安全かつ円滑に実施するには、必要な設備や教材を備えていることが不可欠です。
ここでは基本設備と実地教材の要件を解説します。
講習や審査を安全かつ円滑に行うための設備を整えておくことも、登録講習機関として認定されるために必要です。
具体的には、ドローンの飛行に直結するプロポ(送信機)、オーバーライド用のトレーニングケーブル、予備バッテリー、バッテリーチャージャーなどの器材が挙げられます。
そのほか、パイロンや旗などの目印、風速計やストップウォッチなどの計測機器、保護具や発電機なども含まれます。
夜間での修了審査を行う場合には照明機器も用意しましょう。
学科教材は国交省がサンプルを公開しているため、比較的容易に準備できます。
一方で、ドローンの実地講習には受講者の技能習得を促す教材も必要ですが、実地教材については公式なサンプルが存在しないため、スクールが独自に作成しなければなりません。
そのため、作成の難度が高いとされています。
修了審査を行うには、十分な広さがあり安定してドローンが飛行できる空域の確保が前提となります。
基本的には縦13メートル(安全確保のためのバッファが+2メートル)×横21メートル×高さ5メートルのスペースを占有していることが条件です。
必ずしも所有している施設である必要はなく、賃貸であっても問題ありません。
ただし、最大離陸重量25キログラム以上のドローンの修了審査を行う場合は、より広い縦32メートル×横35メートル×高さ12メートルの空域が必要です。
これにより、安全で正確な修了審査を実施できる環境が担保されます。
講習や審査に用いるドローンは、安全性が確保されている必要があります。
具体的には、対角上のプロペラ中心点の距離が20センチメートル以上あり、風速5メートル/秒程度にも耐えられる強度を持つこと、さらに10分以上の飛行が可能であることが必要です。
加えて、位置安定機能を備え、送信機から解除できる仕組みや講師が操作できる機能も欠かせません。
さらに、プロペラガードが装着できる機体であることや、状況に応じて夜間の修了審査を行う場合は前後左右がわかる灯火、目視外の修了審査を行う場合はカメラなどの追加機能も必須となります。
ドローンの登録講習機関として国土交通大臣の登録を受けるには、講師が定められた条件を満たしていなければなりません。
登録講習機関は、以下の2種類に分類されます。
一等無人航空機操縦士と二等無人航空機操縦士の主な違いは、「レベル4飛行」と呼ばれる有人地帯での目視外飛行ができるかどうかという点です。
そのため、一等・二等のいずれを担当するかによって講師に求められる水準や経験も異なります。
ここでは、それぞれの講師要件について解説します。
等級にかかわらず講師として登録されるための要件は、以下の通りです。
一等講習機関の講師には、高度な技能と経験が求められます。
基本的には、一等無人航空機操縦士の資格を持ち、取得後1年以上の飛行経験を積んでいることが要件です。
特例として、国のホームページに掲載された講習団体で1年以上の講師経験があり、直近2年間で1年以上かつ100時間以上の飛行実績を持つ場合も認められました。
ただしこの特例は経過措置であり、令和7年12月5日に講習団体のホームページ掲載終了と同時に終了のため、国家資格と経験を備えることが必須となります。
二等講習機関の講師の要件は、二等無人航空機操縦士の資格を持ち、取得後6か月以上の飛行経験があることです。
また、移行期の特例として、国のホームページに掲載された講習団体で6か月以上講師経験があり、直近2年間で6か月以上かつ50時間以上の飛行実績がある場合も認められました。
ただし、この経過措置も令和7年12月5日で廃止です。
ドローンの登録講習機関として認められるには、以下の手順を進めることが必要です。
通常は約2か月で完了しますが、書類や手続きに不備があれば半年ほどかかる場合もあります。
登録を受けるための手順をしっかりと確認し、余裕をもったスケジュールで準備を進めましょう。
登録講習機関として登録を受けるには、多岐にわたる書類を整えて提出することが欠かせません。
具体的な必要書類は、以下を参考にしてください。
このように、用意しなければならない書類は多岐にわたります。
漏れがないように準備しましょう。
ここからは、ドローンの登録講習機関としての登録に関するよくある質問と回答を解説します。
可能です。
ただし、全国の各スクールで実施する講習の内容が同じでなければならないため、使用するカリキュラムや教材を統一することが求められます。
新たに登録講習機関として認定を受ける際には、登録免許税を納付(一等9万円、二等9万円、両方行う場合は18万円)する必要があります。なお、登録講習機関の登録期間は3年間です。
登録講習機関の更新を行う際は、登録免許税の納付は不要です。
宿泊施設やレジャー施設を活用して講習を実施することも可能です。
ただし、修了審査まで行う場合には、通常の書類に加えて修了審査用の空域図を提出する必要があります。
シミュレーターでの飛行経験は、講師要件実績には含まれません。
あくまでも、実際に機体を操縦して積み重ねた飛行経験が必要です。
ドローンの登録講習機関として認定を受けるには、要件の確認から膨大な書類作成まで多くの準備が必要となります。
そのため、自力で進めると時間や労力がかかり、登録できないというリスクも伴います。
このような状況で強い味方となるのが、行政書士です。
制度に精通した専門家であるため、申請書類の作成、要件の確認、将来的な監査を見据えた運営体制づくりまでサポートが可能です。
「登録の要件が複雑でクリアできるか不安」「業務が忙しくて申請まで手が回らない」「教材や運営のサポートもしてほしい」と感じる場合は、申請代行を活用することで、安心かつ効率的に登録を完了できるでしょう。
ドローンの登録講習機関の登録を確実に無駄なく進めたいという方は、ドローン関連の業務で日本トップクラスの法務実績を誇るバウンダリ行政書士法人に、ぜひ一度ご相談ください。
ドローンの登録講習機関として認定を受けるには、施設や設備、講師、機体といった多岐にわたる要件を満たし、数多くの書類を漏れなく揃えることが欠かせません。
特に初めての申請では、不備による開校遅延や運営開始後の監査で指摘を受けるリスクも懸念されます。
こうしたトラブルを防ぎスムーズに手続きを進めるためには、制度に詳しい行政書士のサポートが効果的です。
専門家による代行を活用すれば、申請から監査への備えまで安心して取り組めることでしょう。

バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。