
2026.01.26
申請方法(DIPS)

2025.08.19

「ドローンの飛行許可を取りたいけれど、申請書の書き方が複雑でどこから手をつければいいか分からない…」
そんな悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。
ドローンの飛行許可申請は、主に「様式1」と「様式3」という2つの書類を、オンラインシステム「DIPS 2.0」で作成・提出するのが基本です。
各様式には専門的な項目が多く、正しく記入するには一定の知識が求められます。
本記事では、これら申請書の作成でつまずきやすいポイントを項目ごとに整理し、国土交通省のルールに沿った正しい書き方を【記入例付き】で分かりやすく解説します。
申請前に満たすべき条件や申請先の知識も網羅していますので、手続きをスムーズに進めるために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
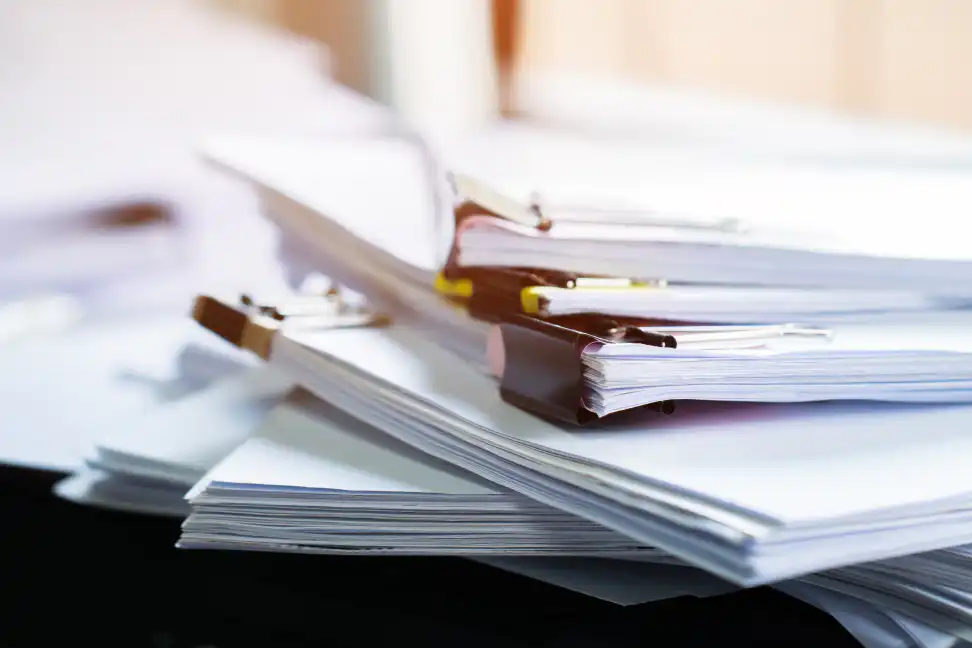
ドローンの飛行許可を得るためには、航空法に基づいた申請書の提出が必要です。
ここでは、申請先や提出方法、そして申請前に満たすべき条件について、順を追って解説します。
ドローン飛行許可の申請先は「国土交通省航空局」または「管轄の地方航空局・空港事務所」のいずれかです。
申請書は適切な部署へ自動的に振り分けられますが、通常の飛行は基本的に「地方航空局(東京航空局又は大阪航空局)」が担当です。
ただし、以下のような特定のケースでは空港事務所へ申請しなければなりません。
基本的にはDIPS 2.0が自動で判断してくれるため初心者でも安心して申請できますが、上記のようなケースでは申請難易度が上がります。
現在、ドローン飛行許可申請はほぼすべてDIPS 2.0というオンラインシステム上で完結します。
申請書の作成から送信、審査状況の確認まですべてこのシステム内で行えます。紙(メール)による申請は審査が遅いため、DIPS2.0を使えない場合に例外的に申請を行います。
DIPS 2.0は以下のような機能を備えており、申請作業が効率的かつ正確に進められるように設計されています。
なお、DIPS 2.0で申請する流れは以下の通りです。
なお、DIPS 2.0が使用できない場合や、どうしても使用したくない場合は紙(メール)での申請も可能です。
その際は、国土交通省の公式サイトから様式をダウンロードし、記入・提出しましょう。
2022年12月の航空法改正以降はDIPS 2.0の利用が一般的で審査も早いため、特別な事情がない限りはオンライン申請を行った方が良いでしょう。
飛行許可を申請するにあたっては、単に書類を出せばよいというわけではありません。
申請書を提出する前に、3つの条件をクリアしておく必要があります。
1つ目は機体登録です。
100g以上のドローンを屋外で飛行させる場合は国への登録が義務化されており、登録された機体には「登録記号」を表示する必要があります。
また、原則としてリモートID機能の搭載も必要です。
2つ目は操縦者の登録で、夜間飛行や人口集中地区での飛行などの「特定飛行」を行うには、操縦者の知識と技量を有していなければいけません。
また、申請時には必要ありませんが、2025年3月からは添付書類だった機体と操縦者の資料を具備し、いつでも提示できるようにしておかなればいけなくなりました。
具体的には以下の通りです。
3つ目は安全管理体制の整備で、第三者への事故リスクを回避するために以下の対策を求められます。
これらの準備が整っていないと申請自体が受け付けられない、あるいは許可が下りない可能性があるため注意しましょう。
ドローンの飛行許可申請書を提出するなら「様式1:無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」の書き方を知っておく必要があります。
ここでは4つの項目に分けて、具体的な記入方法を見ていきましょう。
申請する全てのドローンについて記入が必要です。
ドローンの製造者名、名称、重量、製造番号、登録記号等、仕様が分かる資料(設計図または写真)と所有者情報をドローンごとに記入していきます。
DIPS2.0で申請する場合は、機体登録を行っているドローンしか申請できないため、入力不要な項目が多いです。
また、機体と操縦者については添付不要な資料(作成して具備することは必要)もあるため注意が必要です。
製造番号等は、メーカーが指定している番号だけでなく、自分で設定した番号でも問題ありません。
設定した番号はドローンに表示しなければならないので、忘れないようにしましょう。
航空局ホームページに掲載されているドローン(2025年12月廃止)を申請する場合は、仕様が分かる資料(設計図または写真)を省略することができます。
省略できる場合は、資料を添付・記入する欄に「資料の一部を省略することができる無人航空機に該当するため省略」と記入してください。
DJIの多くのドローンは航空局ホームページに掲載されています。
航空局ホームページに掲載されているドローンでも、改造をした場合は資料の省略ができなくなるので注意しましょう。
申請する全てのドローンについて記入が必要です。
ここにはドローンの性能について記載していきます。
具体的には、最高速度、飛行可能な風速や操縦方法についてです。
ドローンの取扱説明書などを見て記入するか、取扱説明書のページを貼り付けて作成しても問題ありません。
航空局のホームページに掲載されているドローンを申請する場合は(運用限界)と(飛行させる方法)両方に「資料の一部を省略することができる無人航空機」に該当するため省略、と記入します。
航空局のホームページに掲載されているドローンでも改造している場合は、2つのパターンに分かれます。
改造していても飛行性能に影響がない場合は、以下のように記入すれば問題ありません。
「改造は○○の装備(改造の概要を記載して下さい。)のみであり、機体の飛行性能に影響はない。当該機は資料の一部を省略することができる無人航空機に該当するため省略」
飛行性能に影響がある場合は資料を省略できないので、改造が飛行性能に与える影響と改造したドローンの性能について記入する必要があります。
申請するドローンが追加基準を満たしているかどうか確認、記入していきます。
追加基準というのは、人口集中地区(DID)内での飛行、夜間飛行や目視外飛行などの許可の項目ごとに決まっている基準です。
適合性の欄に文章と写真・図面などで説明していきます。
例えば、人口集中地区内での飛行では原則プロペラガードを付けて飛ばさなければいけませんし、夜間飛行ではドローンの向きが見て分かるようなライト(灯火)が付いているドローンを使わなければいけません。
航空局のホームページに掲載されているドローンはここでも資料の一部を省略することができます。
省略できる場合は、適合性の欄には「資料の一部を省略することができる無人航空機に該当するため省略」と記入します。
省略できる許可項目はドローンごとにA~Gの項目が決まっていて、「資料を省略することができる無人航空機一覧」で確認することができます。
この一覧も度々更新されるので、許可申請をする前に、国土交通省のホームページで最新の一覧をチェックするようにしましょう。
ドローンの操縦者に関係する情報を記入していきます。
具体的には、操縦者の氏名・個人の住所・飛ばすことができるドローンの機種です。
備考欄には、技能認証(民間資格)を受けている場合に技能認証名を入力します。
繰り返しになりますが技能認証とは、国土交通省で決めた一定の基準を満たし、国土交通省のホームページに掲載されたドローンスクールが行う技能(実技)試験のことです。
この試験に合格すると証明書が発行されます。
許可申請をするときにこの証明書情報を提出すると、操縦者資料の一部を省略することができます。
10時間以上の操縦経験や、知識面をドローンスクールで既に学んでいるからです。
具体的に省略することができる資料は、(様式3)無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書と無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の部分です。
国土交通省のホームページに掲載されていないドローンスクールが行う技能試験や、国土交通省のホームページに掲載されているドローンスクールが行う技能試験でも、国土交通省に認められていない内容の技能試験の場合は合格したとしても操縦者資料を省略することができないので注意してください。
様式3を記入するなら具体的な書き方も理解しておきましょう。
ここでは重要な2つのポイントについて解説します。
ドローンの操縦者ごとに飛行経験を記入していきます。
許可を取得するためには、最低10時間以上の飛行経験が必要です。
そして、夜間飛行・目視外飛行については具体的な飛行経験時間の決まりはありませんが、あらかじめ飛行経験を積み、安定した飛行ができなければ許可を取得することができません。
最低1時間はしておいた方がよいでしょう。
物件投下許可を取得するためには、5回以上の物件投下の経験が必要です。
物件投下の前後で安定した機体の姿勢制御ができなければいけません。
飛行経験を積むときは、飛行許可が不要な室内や、訓練目的の飛行許可を取得してドローンを飛ばす必要があります。
こちらも国土交通省のホームページに掲載されているドローンスクールが行う、国土交通省の確認を受けている技能試験に合格している場合は記入の必要はありません。
国土交通省で公表している航空局標準マニュアルを使用する場合は、飛行マニュアルの添付は不要です。
添付は不要ですが、許可を取得した後もこのマニュアルの内容を守って飛ばさなければなりません。
オンライン申請でも郵送申請でも形式上、許可申請をするときは申請書にチェックを入れるだけで済んでしまうため、絶対に熟読して内容を理解するようにしてください。
航空局標準マニュアル以外のマニュアルを使用する場合は、そのマニュアルを申請書に添付する必要があります。
飛行マニュアルは許可申請の中でも1番と言ってもいいほど大事な部分なので、必ず覚えるようにしましょう。

バウンダリ行政書士法人
代表行政書士 佐々木 慎太郎
(Shintaro Sasaki)
ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。
無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。